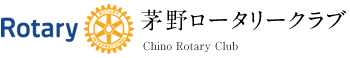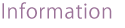五味光亮さん「旭日双光章」受賞おめでとうございます。長年の職業奉仕の結果が認められたものと思います。盛大にお祝いをして、沈滞した経済を盛り上げてください。
新田次郎著「怒る富士」を読みました。江戸時代宝永4年(1707)に起きた富士山大噴火を舞台にした歴史小説です。今から305年前富士山が最後の大噴火(620年ぶり)を起こしています。この噴火で大被害を受けた駿東郡59ヶ村は、小田原藩十万石から藩での復興は不可能として、返地として幕府へ返却された。幕府は復興を諦めた「亡所」とし、住民は「棄民」として見捨てられることになった。
隣の足柄上・足柄下郡も同時に幕府に返却されるが、復興可能として、関東郡代伊奈半左衛門忠順を派遣し、酒匂川の砂除川浚(すなよけかわさらい)奉行に任命し河川改修を勧める。
作者の新田次郎(本名:藤原寛人)は、気象台勤務時に昭和7年から12年まで毎年3~4ヶ月の富士山頂観測所交代勤務員を経験している。 この時、登山口の御殿場の人が強力(ごうりき)として協力した。この人達から駿東郡59ヶ村を飢餓から救った「伊奈半佐衛門」のことを聞き、後年小説家となってから「怒る富士」を書いた。昨年の東日本大震災を経験してみると、300年前の物語が強いリアリティを持っていることに驚く。元禄バブルがはじけた五代将軍綱吉の末期、側用人柳沢吉保が活躍していた頃である。
未曾有の大震災をよそに権力闘争を続ける幕閣の姿、米の石高中心の経済から貨幣経済へ、武士の時代から商人の時代への大転換期、大災害の復旧復興と社会・経済・政治の大転換が東日本大震災後の現在の姿と大きく重なってみえる。震災後一読の価値ある書と思います。
こちらの記事も一緒に読まれております。
Last Update:2012年05月02日