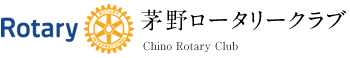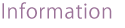私は、1975年に大学を卒業して、その年の公認会計士2次試験に合格して「会計士補」の登録をしました。「会計士補」の振り出しは、監査法人第一監査事務所という事務所です。合併統合を繰り返して、今は「新日本監査法人」という大手監査法人になっています。中央青山監査法人がカネボウ事件に関連して、結果的に解散となり、当時の東京事務所のメンバーと多くの約1000人の規模で、新日本監査法人に移りました。2年間在籍して、一昨年の6月末で退職しましたが、監査法人の最初と最後が同じ事務所で繋がったという奇縁に自分自身驚いています。
東京での第一監査事務所勤務の時代に、主査(監査の現場責任者)として担当した会社のひとつに、住友共同電力という会社があります。愛媛県の新居浜に本社があって、水力発電所や火力発電所で発電した電気を、新居浜を中心とする住友グループの各社に供給するという電力会社です。電力会社の会計は、「電気事業法」という法律に基づいて、「電気事業会計規則」という経済産業省令で詳細が決められています。30数年前の記憶を思い出してみると、当時は国際会計基準のようなものは全く無くて、9電力の経理担当者会議が要望を取りまとめて、通産省に要望して細部の取り扱いが決まるという状況でした。電力会社の決算は電気料金の算定の基礎となるために、監督官庁である通産省の厳重な監視のもとに置かれておりました。詳細は忘れてしまいましたが、減価償却の方法を定率法から定額法に変更するという重大な変更(利益が大きく増加する結果になります)が、いとも簡単に決まったことに驚いたことを覚えています。現在は、IFRS(国際会計基準)や他の規制がとても厳格でこんなことは決してありません。
大震災後の福島原発事件を契機に今ほど電力会社が世の中の注目を集めている時期は無いと思います。東京電力の4半期報告書2011/4/-6を見ると、「現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる」という記載があります。会計の専門家としては、被災した東京電力、東北電力をはじめ、中部電力他の電力会社の今後の決算を注目していきたいと思っています。
こちらの記事も一緒に読まれております。
Last Update:2011年09月14日