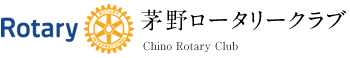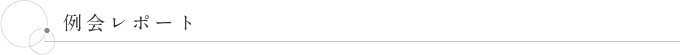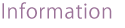原 雅廣 様(NPO法人匠の町しもすわあきないプロジェクト 専務理事)
2010年「長野県 地域元気づくり支援金」県知事賞受賞
(匠の町しもすわあきないプロジェクト)
2012年「地域づくり表彰」国土交通大臣賞受賞
(諏訪アライアンスプロジェクトさいか)
「第3回地域再生大賞」関東甲信越ブロック賞受賞
(匠の町しもすわあきないプロジェクト)
『御田町商店街』は、今から10数年前までは約半分以上が空き店舗だったが、今は空いてるところはほとんど無い。20歳代後半から平均すると40歳代前半の若い人たちが下諏訪へ移住してきて、店をやっている。店舗の半分くらいが「工房」ジャンルの人が多く、デザイナーとか個性的な飲食店とかが店を始めている。
「匠の町しもすわあきないブロジェクト」は、もともと諏訪という地域は工業の街で、観光資源も多いが、実際の産業の主軸は工業だと思っていて、この町の強みである「ものづくり」を「街づくり」に活かせるのではないかと最初のコンセプトとして考えた。
商店街の中で大手量販店のようにモノを仕入れてきて売る商売ではなくて「SHOP」として個性のある店舗としてそこで無ければ買えないという商売をしないと成り立たない。だったら街中でモノを作ってもいいじゃないか、ということで始めた。
じゃあ何をするの、ということで具体的に始めたのは、まず自分たちが「出来ることから始めよう」ということで、まずある「空き店舗」で自分たちで一軒作っちゃおうということだった。総工費10万円。でも実は結構大きな変化があった。何が変わったかというと、周りの人の見る目が変わった。言ってるだけではなかなか通じないが、形にしてみるとなるほどそういうことかと理解された。
街づくりの活動を進める上で、いろんな人が集まると世代差も含め組織運営は難しい、と考え最初から『やれる人、やりたい人』だけでやったらいいんじゃないかという組織をつくった。それが「プラットフォーム型」の組織で、情報とか人材は共有するが、それぞれの事業は「この指とまれ方式」でやる。「餅は餅屋に任せる」という方式でやっている。
この方式で、下諏訪で「三角八丁」というのをやっているが、これには「実行委員会」はない。主催もいない。もともとそれぞれの商店街や観光協会等がやっていたイベントの日を揃えて広告しただけ。各イベントを1枚のマップにまとめてひとつのイベントに見せただけ。それでも毎回1万人くらいの人が来る。当初のマップに比べて現在はやりたいところが増えてマップの密度が違う。最初は8団体くらいだったが現在は50団体強でまったく分からないくらい、分からなくていいじゃないか。これがプラットフォーム型。
街づくりにおいてイベントは見栄えはいいが、イベントが目的ではなくあくまでも手段でありプロセス。最大の目的は「プラットフォーム型」の構造を作ることによっては相互補完・相互支援の関係のネットワークを構築すること。それによって底上げができれば全体が賑やかになってくるのかなっていう感じでやっている。
そうはいっても次の世代にバトンを渡さないといけないので、新しく来た若い人たちが地域のブランドを発信する活動をしている。「御田町スタイル」ということで、彼らの商品を東京に持っていって展示販売をする。「モノ」を売るんで無くて「マチ」を売るという活動。彼らに「下諏訪」という冠を背負わせながら彼らの製品を発信することを通じて、「マチ」を感じてもらう。「この器スゴイね、どこで作っているの、そう下諏訪なの、その街に行って作った人に会ってみたいね」という具合で。「モノ」を売りながら「マチ」を売るという具合である。
商店街がモノを売ることだけではなくて、商店街からコトを売る町に変化する。それがたまたま下諏訪の場合は「匠の町」ということでモノを作る場所に変化させた。結果的にそこに人が集まってきたが、彼らが今までと同じように「ヨソ者」だったら何も変わらない。今度は彼らが町を支えていく役割を背負っていかなければいけない。それによって町の継続性とか持続性とかいうものがつながって行く。彼らにこの街で仕事をすることの意義付けがどれだけできるかが重要だと思っている。
従来の商店街の活性化は、既存の人と新しく来た人との狭いコミュニティでのディスカッションで終わっていたが、「御田町スタイル」だと、「御田町っていいよね、下諏訪っていいよね、諏訪って行ってみたいよね」と言ってくれるような、大きな商圏でのファングループを作ることによって、外との大きなマーケットとの交歓ということが始まると思っている。そうしたパワーを沢山受けることによって町の持続性が確保できるのではないか。
昨年オープンした「マスヤゲストハウス」は、最近空き家となっていた明治時代から続く豪奢な造りの「ますや旅館」を26歳の齋藤さんが改装して始めた。月に200人くらいの人が日本中から集まってくる。夜は「溜り場」となって憩いの場となっている。若い人も来るがおじちゃんおばちゃんたちも来て和気あいあいとやっている。この建物の修繕も「プラットフォーム型」で、彼女のネットワークで全国からので100人以上が集まってお手伝いしている。クチコミで下諏訪に集まるような動きが出てきている、実際彼女もクチコミで下諏訪に現れてたまたまこの物件の契約をすることになった。コミュニティーがまた新しいコミュニティーを生むような動きが出ている。
下諏訪は小さい町で、まだまだ人口が減っていて、老齢化が進んでいるが、それでも「下諏訪っていいよね」という形で沢山の人がこの町にきてくれる。この町に憧れてくれる。そういう町づくりをしたい。
「街づくり」の活動だと、どうしてもモノサシを経済的指標で置き換えて、どれだけ人が来たかとか、どれだけ売り上げあったとか評価する。もちろんそれも大切だが、ここに住む人たちがここに住んでいて良かったと思える町づくりをしていかないと結局は持続性が確保できない。
僕はあえて「幸福度ナンバーワン」というものを掲げていきたい。幸福度という指標をもってきて考えればまだまだやれることがあるのではないかと感じている。実はこの商店街には、跡取りがいるお店は1軒しかない。しかも女性で、今から13年前は僕らの活動に全く参加してなかったが、7年前くらい前から積極的に参加するようになって、今ではいろんなイベントを仕掛けてやってくれている。その子が、「自分と同じ世代の人たちがたくさんいて仲間ができてすごく楽しくなった。それによって私は幸せになった。」と僕に言ってくれた。やはり単純に経済的な物差しをあてるだけではなくて、もう少し違った側面から街づくりに取り組むことが必要なんだと感じている。
Last Update:2015年03月25日