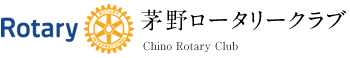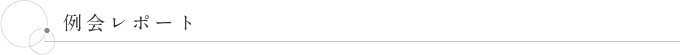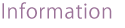皆さんこんにちは、今年は戦後70年です。年頭所の特集で色々な方面からの記事が載っていました。その中で伝統を忘れた日本に「怒」という、
日本文学研究者のドナルド・キーンさんの記事が気になっていました。
記事には、日本の文学は現在、世界の勝者になった。漫画や映画、和食は産業として成功し、小説は数多く翻訳され、ベストセラーになり、美術、建築、さらに生活のあらゆる場面で、日本的なセンスと造形は、世界的な基準になりつつあります。遠いルーツは室町時代の将軍、足利義政の美的趣味にあり、彼の選んだ書院造の簡素なしつらえは、現代人が理想とするシンプルな生活に良く似合う。合理的で洗練され、自然と響き合う日本の美的センスを、すでに多くの西欧人が共有しています。
教育については、問題は日本の国内にあり、海外留学に出る学生の減少が気になります。それでも小学生からの英語が推奨され、自国語の教育を圧迫しています。古文を読む力が国民から失われて久しいが、国文学研究も衰退の一途です。無理もない「源氏物語」の悲哀を行間に味わう暇も与えず、中学・高校では文学ではなく、文法を教え込む。もし書道の授業がなくなれば、日本画の消滅も時間の問題であり、大阪市は文楽協会への補助金を出すかどうか、観客数で判断した。要するに、海外でこれほど価値が認められつつある日本文化を、当の日本人は粗末に扱い続けてきた。そんな70年間であったと言っています。
戦争後、類を見ない高度成長を実現し、多忙だった。とはいえ日本人は過去の歴史や習慣を簡単に手放し過ぎたようです。
芸道についても、語っています。他国は一流の芸術だけがあり、第二、第三はない。素人が参加できる第二芸術がこれほど豊かな国を知らない。格式ある家元制度から地域の集いまで、多種多様な組織が共存し、老若男女が研鑽をつみ合う。それが日本の美意識を支えている。
能・文楽・歌舞伎のファンは世界中で増え、茶道、華道、書道など、日本人の向上心の源である「道」は世界へ広がるだろう。それぞれの土地で翻訳、アレンジされ、21世紀の人類共通の喜びとなる日が、やがて来るのではないか。
その時、本家日本の文化はどれほどの水準を維持しているのか。楽観せずに見守りたい。とありました。
日本文化は世界に認められていると感じることが多いですが、海外の人からみると、日本人の私たちが大切にしていないとみられていると、考えさせられました。
私たちは、日本に誇りを持ち、日本の文化のすべて、道徳・探究心・勤勉
など他国に優れたところがあることを誇りに思って、自国の文化を再認識し残していかなければと思いました。
ドナルド・キーンは
第二次大戦中、日本兵の辞世の歌を翻訳し、「源氏物語」の原文を苦労して読みながら、「日本文学は、いずれ世界を席巻する」と期待したようです。
また司馬遼太郎は「日本学は、かつて辺境の学問であった。キーン教授の半生の労によって、いまでは世界文学という劇場の中で、普遍性というイスをもらっている」と讃えていました。
また、これは戦後70年とは別ですが。文部省の有識者会議でタブレット型の情報端末を使う「デジタル教科書」の導入について、議論が始まりました。
社会のデジタル化は進んでいますが、子供たちが紙の教科書を読み、鉛筆で文章を書くことの大切さは変わらないと思います。
教科書がデジタルになると、子供の興味や関心を呼び起こす効果があるかもしれませんが、いわゆる活字離れに拍車をかけ、活字文化の衰退を招きかねないと思います。ドナルド・キーンさんも、文法を教えて、行間を味わう事がなくなってしまうと言われていますが、デジタル化された情報端末からは何も感じてこないような気がします。
デジタル教科書になると、前の日に時間割を見て明日の授業の準備の必要なくなったり、教科書を忘れて困ることもなくなってしまって、子供のころから忘れ物をしないようにとか、明日の準備をする訓練の機会も少なくなってしまうような気がします。
デジタル教科書は補助教材としての活用にとどめておいていただきたいと思いました。
Last Update:2015年05月27日