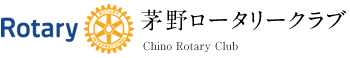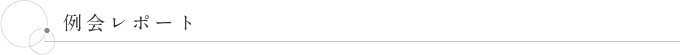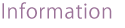皆さんこんにちは、6月7日会長杯のゴルフ大会天候にも恵まれて、楽しい1日になりました。私と北原幹事がワンツーフィニッシュと予想通りの結果が残せて良かったと思います。なお優勝者は小海さんでした。おめでとうございます。
皆さんこんにちは、6月7日会長杯のゴルフ大会天候にも恵まれて、楽しい1日になりました。私と北原幹事がワンツーフィニッシュと予想通りの結果が残せて良かったと思います。なお優勝者は小海さんでした。おめでとうございます。
さて同じく6月7日は、上古田でひとぼしの小屋作りの出払いがありました。
出払いは欠席で会長杯に参加させていただきました。
ひとぼしの本番は6月18日と24日なので、ひとぼしの話をしようと思います。小泉山で行われている、火祭りです。この行事がいつごろから始まったかは明らかではありません。そのいわれも、雨乞い・虫送りなどの豊作祈願、火伏せ・疫病よけなどの安全祈願などと、いろいろ考えられていますが、明確なものはありませんが、茅野市無形文化財に指定されています。12歳を年長に男の子だけで行われます。上古田の他では、下古田・御作田・大日影で行われています。
しばらく離れていたので、私の記憶にある「ひとぼし」の紹介をしようと思います。
5月の連休明けくらいから、毎日曜日弁当を持って小泉山に登ります。最初の頃は遊んでいます。本小屋といわれる1番メインの場所には当時土俵があり相撲を取ったりしていました。年長の者はまず昼飯を食べる小屋を作ります。立木に枝を渡して高床にして、階段と壁・屋根をかけます。葉っぱをたくさん使って、雨が降っても雨漏りしないことの自慢大会をしていました。また強烈な記憶としてあるのは私が小学2年の時だと思いますが、その時の親方が、最年長者を親方と呼んでいました。武闘派で後にどこかで番長と呼ばれるようになった方です。山では親方の命令は絶対で、ほふく前進の練習をやったり、今日は下古田に攻めに行くといわれ、下古田の小屋までみんなで棒を持って攻めに行ったこともありました。今では楽しい思い出です。山で作業があったり、公民館でおんがらで松明を作ったり、本番までは結構やることがあります。当時は松明を作るのに、自分たちで藁から縄をなって縛って作りました。おかげで今でも縄はなえます。それとちょっとしたルールがあって、山に持っていく道具ですが。4年生になると鎌。5年生になると鋸。それ以上になると、鉈を持って行きます。早く鉈持ちたいと思っていました。やっぱ上級生が鉈でばんばんやって、かっこよく見えたのだと思います。上古田の「ひとぼし」は秋葉様・奥ノ院・中段・金毘羅神社がある所を本小屋といい4か所作ります。適当な木を切り倒して御柱のように引っ張ってそれぞれの場所に運び、どんど焼きのような小屋を作り、葉っぱや藁を詰めてつくります。
今は出払いで小屋つくりをしますが、当時は本番の日以外は大人が山に来たという記憶はありません。
当日は、秋葉様の小屋から火を付けます。ここは全員で行います。
この秋葉様が終わると、4年生が下級生を送って一度下山します。4年生は送り届けて、もう一度山に登り合流します。私が4年の時松明が途中で消えてしまい天気も悪かったんだと思いますが、漆黒で1寸先は闇でした。道が分からず登ことが出来なくて、なんとかもう一度下って、近くの家から火をもらって松明に火をつけて山に登った記憶があります。梅雨の時期で当日が雨で燃えなくて苦労してこともありました。現在は子供も少なり、小屋作りも出払いで作るようになり、1度に2つ小屋を作り、18日と24日に燃やしています。
今はやり方等違うこともありますが、伝統を守るということは続けるということがだいじだと思います。今でも楽しい思い出です。
実は、昨年会長の任期が始まる前、挨拶困ったなと思っていました。6月になれば、ひとぼしの話もいいかなとか思っていましたが、今日この会場での最終例会を迎えることが出来き、ひとぼしの話も出来ました。本当にありがとうございました。
また今日の食事の後のデザートはマリオさんからの1年のお礼という事で、いただきました。ご報告いたします。
Last Update:2015年06月10日