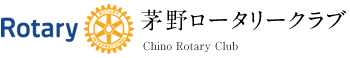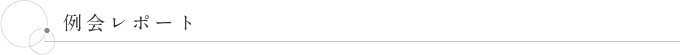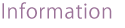皆さんこんにちは。8月15日は終戦記念日でした。この時期になると否が応でも戦争と平和の事を考えざるを得ません。
先日、下伊那にある満蒙開拓平和記念館へ行ってまいりました。この記念館は人口約6600人の阿智村にある記念館で、私と同じ不動産鑑定士をしている友人の寺沢秀文さんが専務理事をしており、平成25年4月に開館した平和記念館であります。私も少しですが寄附をさせて頂きました。
この記念館は戦時中国策で、旧満州国に多くの日本人が渡り入植した 「満蒙開拓」の資料を収集展示してあります。当時の映像、写真、手紙、資料や住居の模型が展示されており、入植から逃避行、集団自決、収容所の生活、そして中国残留孤児等の負の歴史を目の当たりにし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを学ぶことが出来ます。
ここで日本の歴史を振り返ると、昭和6年に満州事変が勃発し、そこから15年戦争の出発点となります。昭和7年には満州国建国。満州への移民については 武装移民から、分村、分郷移民、さらに青少年義勇軍とさまざまな形で終戦間際まで続きます。満州移民については,私たちの住む長野県が突出した形で行なわれました。
この満蒙開拓は、満州事変から第2次世界大戦終戦までに、旧満州に約30万人が入植した国策です。特に長野県は県や教育会の指導や、養蚕・製糸業の不況から全国最多の約33,000人が入植しました。「20町歩(20ha)の地主になれる」との国のスローガン(これを「王道楽土」といったそうですが)が掲げられ大陸に渡りましたが、厳しい自然の中で開墾や敗戦、シベリア残留等を経験し、帰国できたのは3分の1程度と言われております。逃避行の途中で子どもや家族を失い、一部は中国残留孤児となりました。引き揚げ帰国できた人々も荒れ地に居住させられ、県内各地に「満州開拓殉難の碑」が残されております。私たちの住む諏訪のエリアからは、富士見村から渡った人が最も多く、富士見村と落合村の計約1,000名が参加し、現在の中国黒竜江省にそれぞれ村を形成した様です。
富士見村の経済資料によれば、昭和12年のこの村の平均年収は473円で、他県と比べるとかなり低く、平均的な借金は734円位あったそうです。政府は 「満蒙開拓義勇軍」を募る際に、奨励金として1世帯当たり1,000円を保証したそうです。当時農林省は「富士見村」を「経済更正指定村」に指定し、その翌年、村議会は分村移民を決定しました。分村移民によって満州に渡った人は人口4,715人のうち984人と全体の約2割に相当しています。又、長野県立歴史館の企画展の資料によれば、帰還率は幸いなことに富士見村は70.5%となっており、下伊那地区の村は35%~40%前後となっていることから、入植した場所にもよりますが、長野県の下伊那地区に中国残留孤児が多い理由を裏付けます。
最近、この満州からの引き揚げの状況を題材とした、藤原ていさんの「流れる星は生きている」を読み直しましたが、ていさんと3人の子供の引き揚げの壮絶な様子は涙を誘います。皆さんご存知だと思いますが、藤原ていさんは諏訪市の出身で、旦那さんは作家の新田次郎さんで、その次男は数学者であり あの「国家の品格」を書かれた藤原正彦さんです。藤原正彦さんもまさに、この満州からの引き揚げを経験されており、その後の人生のバックボーンとなっている様に思います。
今年は終戦から70年目となります。今 国会で憲法改正について色々論議されておりますが、二度と戦争をしてはならないと思います。そのことを考える時、高邁な思想はともかくとして、身近な足もとから見つめ直してみたらどうでしょうか。
Last Update:2015年09月16日