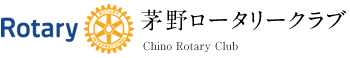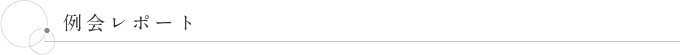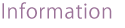10月は健康診断月間ということで、私も20日に池田先生の所に健康診断に行ってきました。結果は、血管年齢90才、血圧170という、昨年と全く変わらない、散々な結果でした。検査の1週間くらい前からは、河原の湯で血圧を測り、だいたい140前後だったので、今年こそはと、意気込んでいったわけですが、その力みが裏目にでたのか、170という残念な結果に終わってしまいました。池田先生からは「そろそろお医者さんと仲良くなったほうがいいですよ」と優しい声をかけていただきました。私は昨日11月1日が誕生日で、61才になりました。しっかり高齢者ですので、頼れるのはお医者さんですので、池田先生とは是非仲良くしたいな、と思っていますので、よろしくお願いします。
さて、今日の話ですが、10月31日が「そばの日」ということで、お蕎麦の話をしたいと思います。11月に入り、いよいよ新蕎麦の季節となりました。私も健康のためもあり、週1~2回お昼は蕎麦屋へ行って、ざる蕎麦を食べます。
ある人が「小諸そば」という、首都圏で最大の店舗数を展開するチェーン店の立ち食いそば屋で蕎麦を食べた時、若い店員から「他の客から、あなたのそばの啜り方がうるさいと苦情が出たので静かに食べて下さい。」と言われびっくりしたそうです。
落語でも、そばの啜り方が芸の見せどころになっているように、そばはつゆを付けて、勢いよく啜ることによって、その美味さが引き立つ、日本の食文化です。それが立ち食いそば屋とはいえ「啜り方がうるさい」と苦情を言われるとは思いもしなかったそうです。
「小諸そば」という屋号ですが、小諸産のそば粉を使っているわけでもなく、小諸市とは全然関係ないそうで、創業者が全国各地のそばを食べ歩いた際、小諸で食べたそばに感動を受けたことから、屋号を「小諸そば」にしたそうです。
創業者の思い入れだけで、地名が利用されているわけで、食品の不当表示にならないのか、消費者庁表示対策課に確認したところ、「消費者に著しく誤認を与えるかどうか」が判断の基準になるということで、店内に実際の産地とは違う産地を連想させるような、小諸のそば畑などの写真を貼ってあると、不当表示の可能性が高くなるそうですが、もうすでに看板だけで誤認を与えていると思えてしまいます。
日本のそばの自給率は、わずか24%にすぎず、あとは輸入に頼っており、輸入量の85%は中国、13%をアメリカからの輸入が占めています。
日本人が食べる日本蕎麦は、圧倒的に中国産です。この中国産が「信州そば」に化けるカラクリがあります。ファミリーマートのプライベートブランドで「信州そば」と商品表示された乾麺が販売されています。そこには<自家引き挽きしたそば粉を使用。のどごしの良い細めのそばです。>とまで添え書きがあります。製造元は長野県戸隠の製麺会社です。その会社に、どこで収穫されたそばを使用しているのか、聞いてみたところ、中国産もしくはロシア産のそば粉を使っています、という答えが返ってきたので、それで「信州そば」と表示することが許されるのか尋ねたところ、「信州そば」の表示には、法的な決まりはありませんが、長野県内で製麺された商品については、「信州そば」と書いていい、という全国乾麺協同組合連合会のガイドラインに沿って商品表示しています、と言われたそうです。中国産のそば粉でも長野県で加工すれば「信州そば」になるわけで、それっておかしいでしょう、と言いたくなりますが、以上で会長挨拶を終わりにします。
Last Update:2016年11月18日