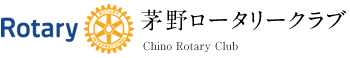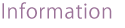「犯罪の危険から自らの安全を守る、さらに社会の安全を守るのにはどうしたらよいのか」
茅野警察署長 児平清光 様

1.はじめに
●いま、社会の安全の問題は、警察任せにしておけばいい?
・2003年頃まで、日本では比較的安全が保たれていたこともあって、社会の安全を守るための仕組みづくりについて、大学をはじめとする研究機関の中で積極的な議論はされてこなかった。
・現在、学問的研究の場においても、観念論ではなく、現実を認識した上で制度のあり方を研究する必要がある、という考え方が広まっている。
・警察を含む行政機関の国民による統制という面に関しても、透明性の確保の観点から情報公開や、政策評価といった制度が導入されてきている。
●社会安全政策のあり方
・現状がどのようになっていて、どうすればコスト(お金《税金》、国民の側の権利自由を制約するような負担も含む)と正義の観点から、より適切な、最も合理的なものが見い出せるかを考える。
●犯罪を引き起こす社会的原因への対策
・ポイント
犯罪を犯しやすいと思われる人間を対象にした対策をとるというのではなく、犯罪の背景につながり得るような事態を減らすことにより、全体としての犯罪を減少させようとするもの。
・4つの課題
①犯罪を犯す背景にある社会的状況の改善
②家庭・学校・地域社会における教育機能の促進
③少年の健全育成を害する要因の削減
④心の荒廃をもたらす状態の解消
2.家庭・学校・地域社会における教育機能の促進
●非行少年の家族関係
《少し前のデータ、少年鑑別所での鑑別担当者の評定》より
・親の指導力不足が男女とも50%を超えて最も多い
・「交流不足」「しつけ不足」がそれに次ぐ
・「家族の問題なし」は男子で約10%、女子で約5%
●教師の権威を認めず、生徒と同様に位置づけるような主張の積み重ね
●地域社会における伝統的な地縁的人間関係の希薄化
3.市民の自発的な活動を継続可能にするために
●犯罪行為やあるいは犯罪ではなくとも、社会の倫理的価値観や共通の道徳といったものをあからさまに損なうそうな行為が頻発し、その状況が多くの人の目に見える事態は、人の心を荒廃させる。
●この秩序感の喪失は、犯罪に対する人々の抵抗感をなくすることを通じて、犯罪の発生を招く。
●それゆえに、社会の秩序感の回復と、その維持にあたっては警察による検挙も必要だが、それ以上に地域社会における取組みがより重要となる。
※地域におけるリーダーの皆様の他、「社会の安全」の問題に積極的に取り組まれる方々の何らかの参考になれば、との思いで、本職の警察行政経験と社会安全政策論資料などに基づいて、私見を申し上げたものです。
こちらの記事も一緒に読まれております。
Last Update:2012年08月08日